夏目漱石の『行人』を読み始める
この時期の漱石はとても読者を意識している気がする。
新聞に連載されていたということがよくわかる。
章の最後でしばしばもったいぶる。
こういう書き方はある程度、話の全貌が見えていないとできないのではないか。
と、読みながら考えている。
書きながら話が作られていくというのがわりと一般的だと思うが、この時期の漱石はそう思わせない。
『三四郎』『それから』は物凄い情熱と勢いで書き上げられた感じがする、とびきりの作品だと思う。
あわせて読みたい


夏目漱石『それから』
『それから』を読み終えた 圧倒的な最後に、ため息が出た。 自分がこれから何か小説を書く必要はもうないような打ちのめされた気分だ。 これが明治の時代に書かれて毎日…
最近読んだ後期三部作。
『彼岸過迄』『行人』(まだ読み始めだが)は結構、最初から設計図があるような気がする。
そう考えると、同時期に書かれた『こころ』もすごく計算されたものの様に感じてくる。
しかし、『こころ』は自分には特別な作品なので、この流れで他の作品と一緒くたにできない。
そして『こころ』の評価というか、作品に対する読者の好みは分かれる。
『三四郎』が最高傑作だという人は多いが、『こころ』の評価はとてもいびつである。
もちろん、僕は大好きな作品だが。
梅田のステーションで降りるやいなや、自分は母からいいつけられたとおり、すぐ車を雇って、岡田の家に駆けさせた。
これが『行人』の冒頭だが、今、読んでも素晴らしい書き出しだと思う。
東京にいる(これまでの漱石の小説の主人公の)誰かが、大阪に来て、おそらく母の代理で何かを頼みに来たんだろうと想像できる。
特に漱石の読者にとってみたら、多分、仕事の周旋か、年頃の娘の結婚相手か、それぐらいだろうと思ってしまう。

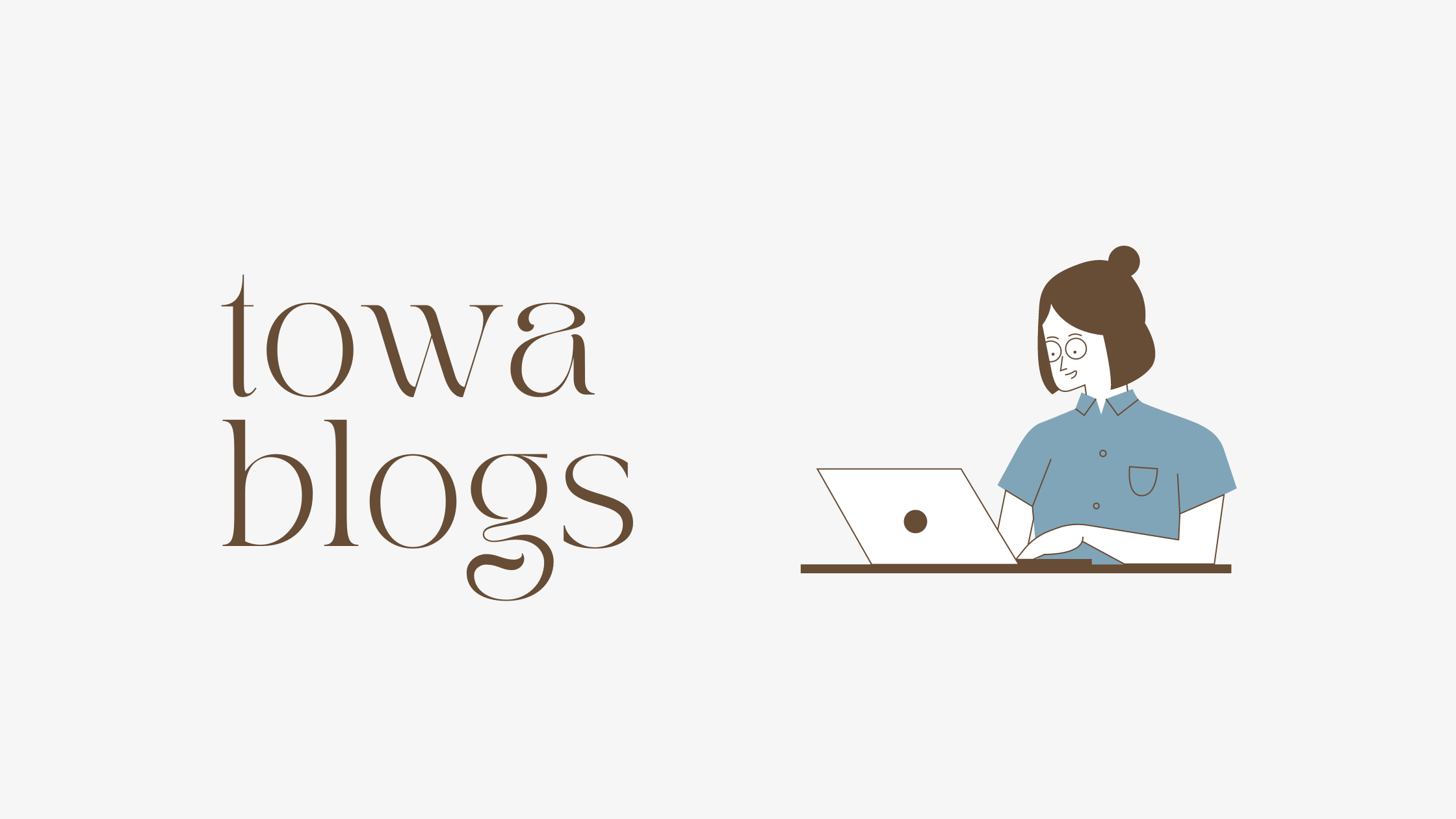


コメント