
1998年のアメリカ旅行 第6章
8月30日 午前4時、ボストン
そこはもう夏が過ぎたあとだった。
昨夜の夜行バスでボストンに向かった僕だったが、いざ着いてみるとそこは凍てつくほどの寒さだった。
時刻が午前4時とあって周りは暗く僕はどこへも行くことも出来なかった。
何か温かいものでもと思ってみるのだが、周囲にある売店など、どこも開いていなかった。
半袖一枚の僕は仕方なく丸く、うずくまって時間を待った。
そうこうしているとセキュリティーの男が近づいてきて、何をしているのか訊いてきた。
けれど僕も寒さのあまりか、それともこういう局面に慣れてしまったのか、往復の帰りのチケットを見せて、始発のバスを待っていると言って、何でもなかったように乗り越した。
この旅で僕は随分、嘘が上手くなった。
この国で一人で生きていくには多少の嘘も必要だ。
それも言ってみれば強さだ。
僕には、もう少し強さが必要かもしれない。
しかし今、僕が最も必要としているものは、この寒さを凌ぐための長袖とホットコーヒーだ。
このままでは凍え死んでしまうのではないだろうか。
もの凄い睡魔が更なる追い討ちをかける。
僕は冬の登山モノの映画の遭難シーンにありがちな、寝たら死ぬぞを思いだしたので、何とか目をパッチリ開いていた。
そんな寒さだ。
上手く言葉で伝わるだろうか。
宿探し
そうこう思っているうちに少しずつ明るくなってきたので、僕は動きはじめた。
どうやら足は凍ってないようだ。
僕は少し歩いて地下鉄の駅へ着いた。
実は僕はもうひとつしなければならないことがあった。
それはコーヒーを飲むことでも、寝ることでもなく、今夜の宿を探すことだった。
というのは実は、1週間前にボストンのユースホステルに予約の電話を入れたのだが、僕の訪れるこの日は満員で、予約がとれなかったのだった。
ボストンは観光地として名高いので、いつでもどこでも人がいっぱいらしいのだ。
賑やかなのはけっこうなのだが、いざそこから自分がはみだしてしまうと、その街に嫌気がさしてしまう。
そんな悪条件の中で、僕は安宿を見つけることが出来るのだろうか。
所詮は僕とて、ありきたりな人間なのだ。
寝床が見つかるまで落ち着いてられなかった。
そして、宿を探すにも何ひとつあてのない僕は、しかたなくユースホステルに行ってみることにした。ひょっとしたら一つぐらいベッドが空いているかもしれない。
そう少なからず考えていた。
常に世の中は甘いものだと考えているらしい。
受付に行くと僕は、この旅で覚えた英語をやってみせた。
「ドゥーユーハヴアベッドトゥナイト?」
けれど、空きのベッドはひとつもなかった。
受付の係りから発せられる「ノー」がすこぶる冷淡で僕に違う汗をかかした。
けれどそれにもめげず、他に安くで泊まれるところは知らないかと訊ねた。
すると受付はさらに冷淡に手元の引出しから一枚の紙を取り出し僕に渡した。
とにかく礼を言う僕「さんきゅ」と。
僕が手にしたのはボストンの安宿のリストアップ用紙だった。
探せば結構あるものだな。
そう思い僕は最も安いプリコットハウスというところに電話をした。
電話でのやりとりも旅の前半と比べると随分と上手くなっているのを、慎ましげに感じた。
旅の運気は上々。
僕は話の末、なんとかそこに泊まれるようになった。
受付の気が変わらぬうちに僕は急いでそこへ向かった。
着くとそこは、街はずれのとても静かなところにあり、観光地とは思えないぐらい人が少なかった。
けれどそれがかえって、少し疲れた僕を和ましてくれた。
僕はチェックインするまで随分と待たされたが、その待合所のリビングにはコーヒーのサービスがあったので、僕はついつい二杯三杯と砂糖いっぱいのコーヒーを飲んで時間を潰すことができた。
運良くコーヒーも飲めてとても気分がよい。
もう僕のすることは眠るだけだ。
そう思っているとホステルの受付の男が僕の名前を呼んだ。
そこで働いているスタッフは皆とても親切で僕が今日まで泊まってきたホステルの中で最も居心地のよいところだった。
午前十一時、僕はようやく寒さから開放された。
30 Aug 1998
8月31日 よそ者
疎外感
ボストンは日本人が多すぎる。
どうしてこんなことになるのかすれ違う日本人がやけに煙たい。
あちらでは決してそうは思ってもないだろうが、思ってくれれば幸いだ。
僕自身、利己的な考えの持ち主ではないのだが、どうもここにいると敵がい心を覚える。
彼らの目が僕にここへ何しに来たのだと問いかけるように見えて仕様がない。
大西洋
ニューベリーストリートを横目で流し、ブルーラインに乗って、少し離れたレバービーチを目指した。
海を見るのが好きだった。
電車を降りるとそこは海の青に包まれていた。
少し肌寒いが、幾人かの泳いでいる姿が確認できる。
まだ夏の海として存続しているのだ。
しかし、いつもの海とは顔が違っている。
何か、同じものなのに少し違って見える感じ。
ちょうど小さい頃、初めて西洋人を見たあの感じを思い出しているようだ。
僕の見ている青はいつもより新鮮であるがやはり幾分、よそよそしい。
いや僕がなにより、その、よそ者だ。
そこは大西洋。
初めて見る海だった。
31 Aug 1998
9月1日 膨大な言葉の熱狂
再び新しい月を迎えることが出来ました。
同時に独りきりで旅をすることがだんだん面白くなってきた。
今までは、こんなものだろうと適当な分別をつけていたが、少しずつ見えてきた。
ここに来て僕は強く何かを感じている。
もちろん、それはエクスタシーとかいう類いのものではない。
熱狂的でありたい。
それだけだ。
僕らしい。
僕のらしさは、一行では完成されない、膨大な言葉の熱狂だ。
1 Sep 1998
9月2日 話し相手は台湾人
今日は少し腹を立てていた。
僕が大人でもう少し大きな心があれば何でもないことだった。
喜ぶべきことだったかもしれない。
けれどもそんな局面を上手く受け止められない青さが僕にはある。
実はボストンに来て知り合った何(Ho)という台湾人の男に僕は腹を立てていたのだ。
出会った時はそんなこともなかったのだけど、ある一つのことが酷く僕を苛立たせたのだ。
それは何であるかというと、彼は中国語を話すのだ。
こういう書き方をすると当たり前ではないかと言われるのだけど、僕が言いたいのはそういう当たり前のことなのだ。
僕が日本人で日本語を話すように、彼も母国語である中国語を話す。
それはそれで、大いに結構だが、彼は僕にも中国語で話してくるのだ。
普通、アメリカで異国の者同士が、話をするなら英語だ。
英語が下手でも、話そうと努力をするのが当然だ。
それでも話すことが出来ないのなら、黙っていればいい。
僕などいつも黙っている方だ。
話せばどうせ内容のない愛想笑いなのだから、黙って自分が何を考えているのか察してもらった方が自分の値打ちを下げることもなく済む。
だから、僕と何(Ho)は話をする必要などなかったのだ。
けれども僕らは三日三晩、話をしている。
それも中国語でだ。
しかも僕の専攻が中国語ともあって、少なからず理解できるから堪らない。
勉強になるから良いではないかと思えれば僕も大人だ。
けれども僕が少し中国語がわかるからといって、一方的に話をしてくる図々しさが許せない。
彼も悪い人ではないのだけど少し繊細さに欠けるところがあったので、僕も嫌ってしまったのかもしれない。
2 Sep 1998
9月3日 物乞い
道端に坐って紙コップを持って中に入った小銭をジャラジャラといわしている。
金をくれとのことだ。
そんな人が山ほどいる。
厭というほど見てきた。
最初は凄く途惑った。
けれど1ヶ月も経つと、それが慣れて公衆電話を見つける感覚で彼らの前を通り過ぎてしまって、深く考えることがなくなった。
或いは深く考えないようにしていたのかもしれない。
とにかく僕は知らないふりをしていた。
「1ドルくれ」。
今日、久しぶりにせがまれた。
もちろん、断わった。
僕は一ヶ月の間に反射的に断わる習慣を身につけていた。
事情も聞かずに断わるのは人道的ではないと思われるが、結局、選択肢は二つに一つなのだから、聞いてもどう仕様もない。
あげるかあげない。
僕の回答は言わずと知れている。
人に頼るな、自分のことは自分で面倒を見ろ。
こんなことを書けるのには僕の旅が順調だからかもしれない。
旅も終りに近付いて余裕が出来てきたからでもある。
他人のことを考える余裕なんて、旅の開始当時は一つもなかった。
随分、無責任な過程を経てきたものだから、幸せ者だ、僕は。
そんな中、旅を振り返るわけでもないが思うことがある。
「もし、僕が盗難にでもあって、一銭もなくなっていたら、どうしていたんだろう?」
3 Sep 1998



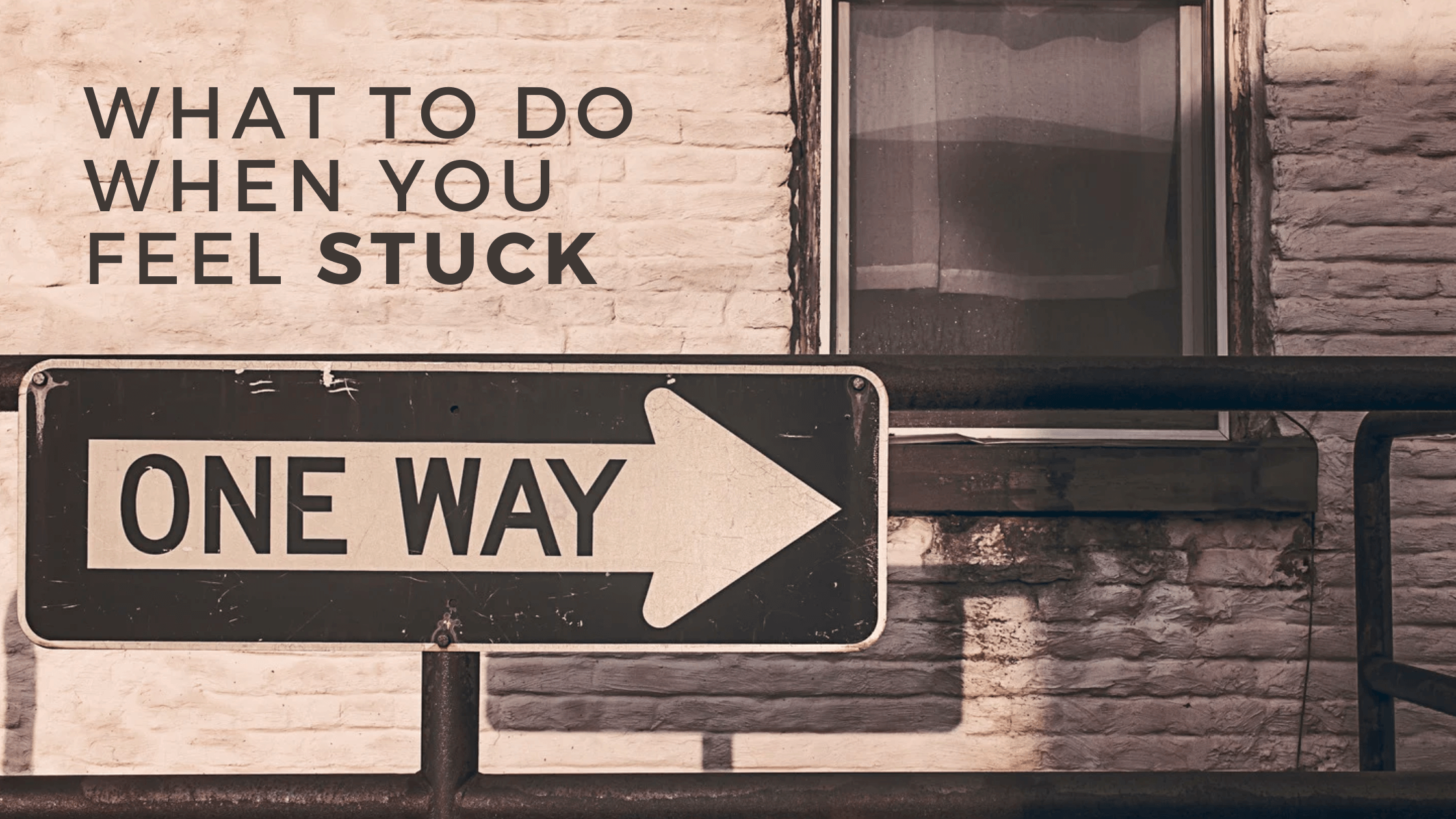
コメント