5日ぶりに自炊を始めたという話を書いていたら・・
突然、また大きな地震が来た。
長いこと揺れているなあと思ったら、僕自身が震えていた。
心臓がバクバク言っていて、これはもう駄目だと思い、
好きな小説の好きな一節を書き写すことにした。
僕なりの写経である。
テレビもラジオも消して、モーモールルギャバンのCDを聴きながら、
大好きな小説を一気に書きなぐった。
・・・そうすると少し落ち着いたので、枕を書くことにした。
早く職場に行きたい。
記憶というのは小説に似ている、あるいは小説というのは記憶に似ている。
僕は小説をかきはじめてからそれを切実に実感するようになった。記憶というのは小説に似ている、あるいは云々。
どれだけきちんとした形に整えようと努力してみても、文脈はあっちに行ったりこっちに行ったりして、最後には文脈ですらなくなってしまう。なんだかまるでぐったりした子猫を何匹か積みかさねたみたいだ。生あたたかくて、しかも不安定だ。そんなものが商品になるなんて――商品だよ――すごく恥ずかしいことだと僕はときどき思う。本当に顔が赤らむことだってある。僕が顔を赤らめると世界中が顔を赤らめる。
しかし人間存在を比較的純粋な動機に基づくかなり馬鹿げた行為として捉えるなら、何が正しくて何が正しくないかなんてたいした問題ではなくなっている。そしてそこから記憶が生まれ、小説が生まれる。これはもう、誰にも止めることのできない永久機械のようなものだ。それはカタカタと音を立てながら世界中を歩きまわり、地表に終わることのない一本の線を引いていく。
うまくいくといいですね、と彼は言う。でもうまくいくわけなんてないのだ。うまくいったためしもないのだ。
でもだからといって、いったいどうすればいい?
というわけで僕はまた子猫を集めて積みかさねていく。子猫たちはぐったりとしていて、とてもやわらかい。目がさめても自分たちがキャンプ・ファイアのまきみたいにつみあげられていることを発見した時、子猫たちはどんな風に考えるだろう? あれ、なんだか変だな、と思うくらいかもしれない。もしそうだとしたら――その程度だとしたら――僕は少し救われるだろう。
ということだ。
(村上春樹『午後の最後の芝生』)
追記@寝る前
久しぶりの自炊は薄味に感じた。
外で食べる食事がいかに塩分が高いのかがわかるナ。
TFMにサンドの二人が出てる。
みんながやさしくなればいい。
あとこれ さっき書いた好きなバンドについて。
あと 奈良さんのブログ。
二つとも、いいなあと思いながら読んだ。
さて、寝るか。
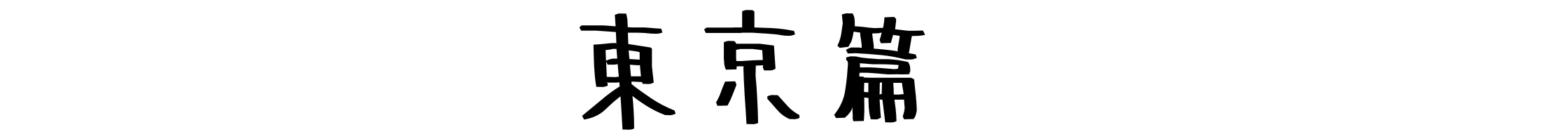









コメント